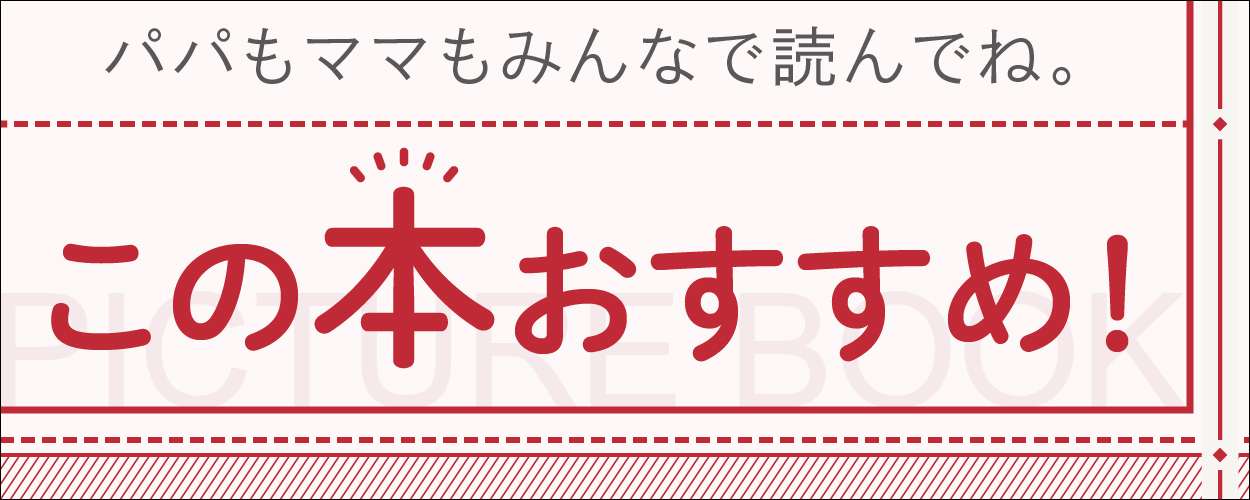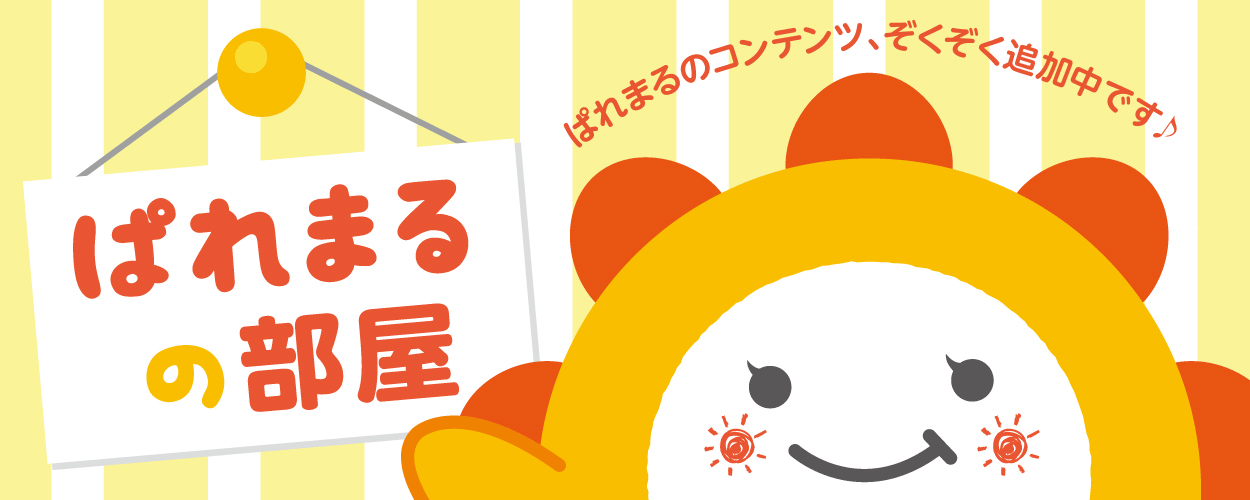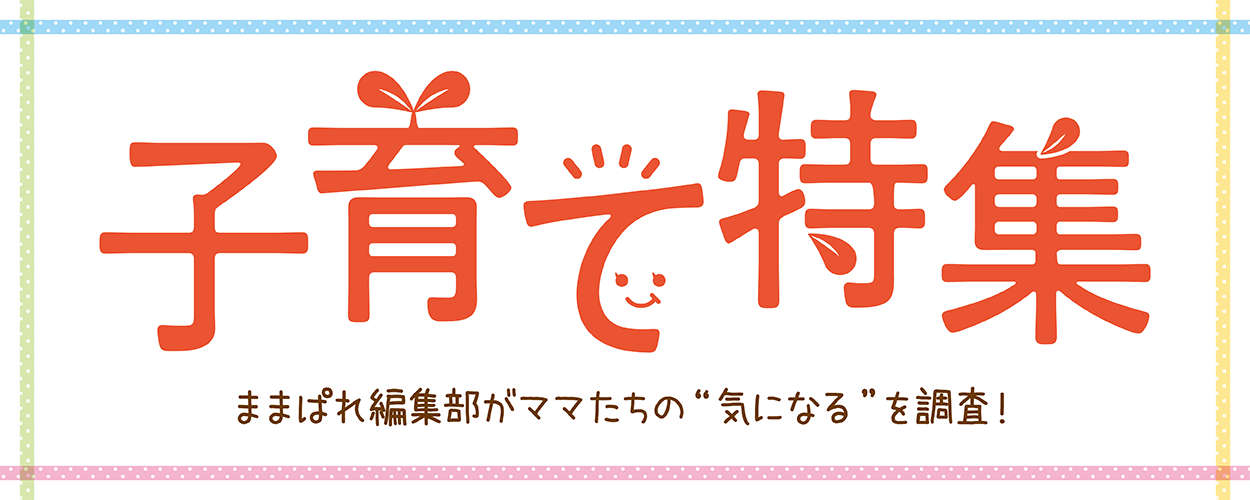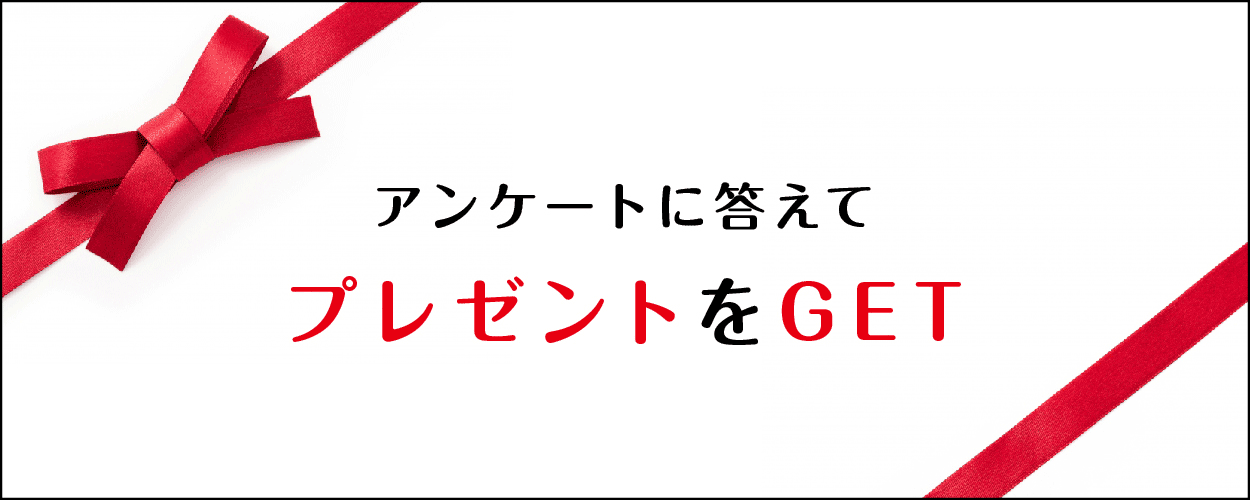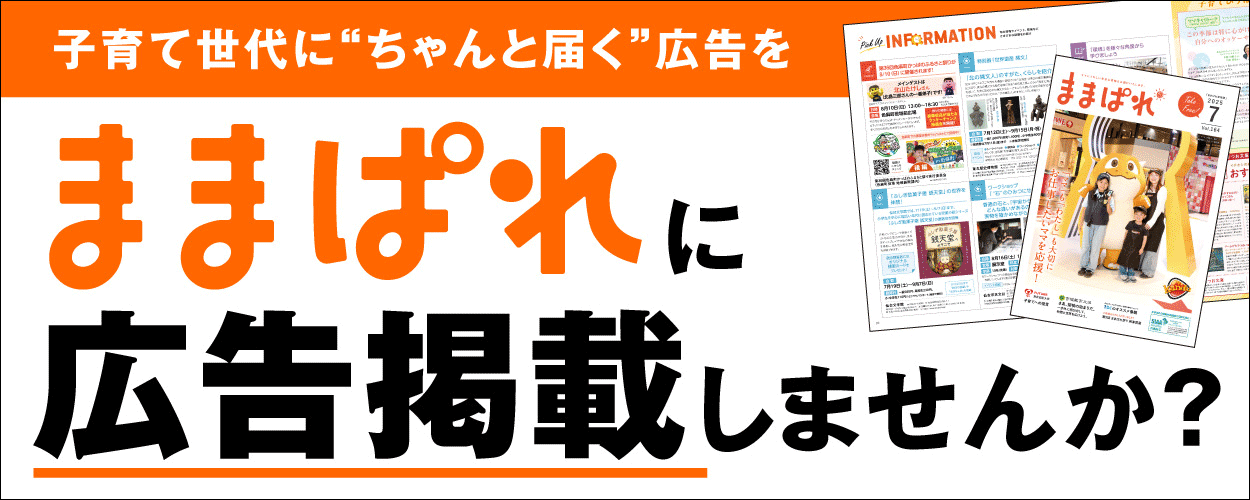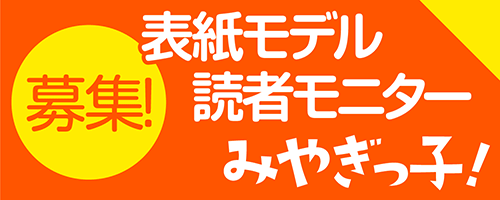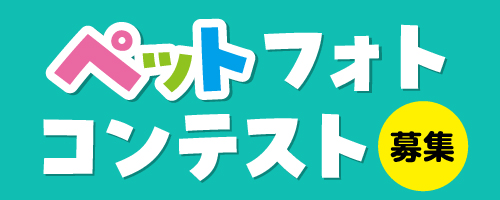家庭科は自分事!思い描く生活と未来を実現する 知恵を身につけよう。
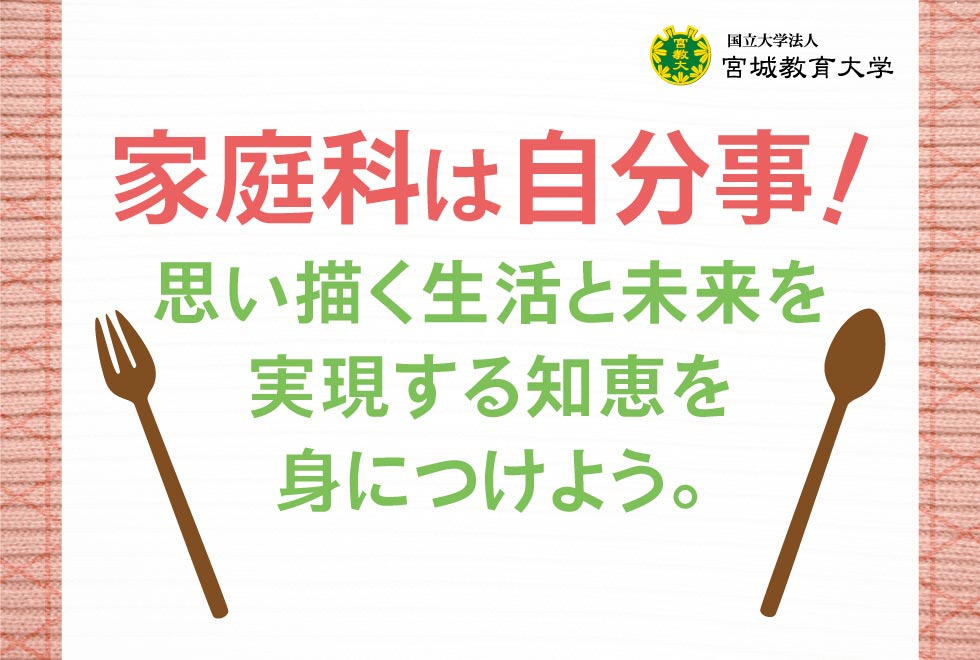
家庭科といえば調理実習だよねと思いつつ、取材準備で高校家庭科のカリキュラムを見てびっくり。
人生設計から子育て、介護や防災まで、まさに「生きる力」そのものでした。
「家庭科は受験科目と違って、些末で世の中から評価されない内容を教わるという感覚をちょっと変えたい」
という先生の一言に納得です。

誰がどんな行動をしたら、世の中が持続可能で、みんなのウェルビーイングが達成されていくかということを、学校ならば消費者教育で共に学んでいくことができると考えました。
前田 まどか 先生
兵庫県出身。静岡大学教育学部で消費生活科学を専攻。高校の家庭科教諭として教鞭を執りながら兵庫教育大学大学院(修士課程)学校教育学研究科で教科教育実践開発専攻。2022年4月から宮城教育大学講師。
高校家庭科で学ぶ内容の広さに驚きました。社会科のようですね。
 共通する部分はかなりありますね。裁縫や調理がメインとされる時代もありましたが、今は育児や介護も含めて家族のこと、法律や環境のこと、消費生活や投資など幅広く学びます。私自身、家庭科の学びには消費者教育の視点が欠かせないと考え、高校の家庭科教諭になりました。宮城教育大学では主に小中学校で家庭科を教えることを想定して授業をしていますが、私は高校教員生活が長かったのでその時の話もしています。高校の家庭科教諭は楽しいですよ。今年はゼミに学生が4人所属しているのですが、生活と信用の関わりを学ぶ授業研究や、防災教育、家族と生活設計、SDGsも絡めた食生活の授業について研究しようとしています。自分の生活と学びがどう繋がっているか幅広く考えたい人におススメの教科だと思います。
共通する部分はかなりありますね。裁縫や調理がメインとされる時代もありましたが、今は育児や介護も含めて家族のこと、法律や環境のこと、消費生活や投資など幅広く学びます。私自身、家庭科の学びには消費者教育の視点が欠かせないと考え、高校の家庭科教諭になりました。宮城教育大学では主に小中学校で家庭科を教えることを想定して授業をしていますが、私は高校教員生活が長かったのでその時の話もしています。高校の家庭科教諭は楽しいですよ。今年はゼミに学生が4人所属しているのですが、生活と信用の関わりを学ぶ授業研究や、防災教育、家族と生活設計、SDGsも絡めた食生活の授業について研究しようとしています。自分の生活と学びがどう繋がっているか幅広く考えたい人におススメの教科だと思います。
家庭科は教えることは膨大なのに1週間に2時間しか授業がないので、ほとんどの先生方はプリントなど自作教材を工夫して教えています。各校で先生方が力を注いで作られた教材や経験を共有する繋がりやコミュニティを作ったり、家庭科の先生方を応援できる存在になりたいと考え、研究に取組んでいます。
消費者教育を教えようと考えた理由は?
遡ると、実家が米と神戸ビーフを育てている農家ということが関係していると思います。子どもの頃から、消費者側が作り手のことを何もわかっていないことに対する驚きと疑問がありました。幼稚園や小学校の写生大会で同級生がうちの牧場に来た際、父が黒毛和牛を「これは肉として食べる牛です」と説明した時に、友だちが「可哀想」と言ったことに衝撃を受けました。みんなが喜んで食べている牛を、家族が休日もなく一生懸命育てていることを想像せずに放たれた一言に隔たりを感じました。また、BSE問題(※1)が起きた時は、うちのような農家だけでなく、販売、調理する業者も消費者も影響を受けました。この問題をきっかけに牛トレーサビリティ法(※2)が成立したわけですが、すべての農家が責任を持って育てていくために必要な制度や、販売されるまでの過程が公開される仕組みが整えられていくのを見たことも、私が消費者教育に取り組む理由だったかもしれません。
病院での支払いが3割以下の負担で済む健康保険の仕組みや、スマホで課金・決済すればほしいものが手に入る仕組み、大人も子どもも意識せずに、その恩恵を受けているでしょう。また、搾取されている人のことを考えず、good price(お買い得)のものを好んで買ったりすると思います。誰がどんな行動をしたら、世の中が持続可能で、みんなのウェルビーイングが達成されていくかということを、学校ならば消費者教育で共に学んでいくことができると考えました。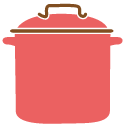
※1 BSE問題
BSEとは、1986年にイギリスで初めて確認された牛の病気で、狂牛病のこと。これにより食の安全が叫ばれた。
※2 牛トレーサビリティ法
牛の個体識別番号を管理・伝達することで、国産牛肉の安全・安心を確保するための法律。
最近では消費者意識も変わりつつありますね。
近年は、ある商品が完成するまでの物語への興味が商品選択の理由となる、という考え方が消費者に浸透してきたので、求めに応じる商品やサービスを目にする機会も増えたのではないでしょうか。消費者教育を学んだ仲間や後輩は、企業で働く人もいますし、消費者庁や国民生活センター、地域の行政を支える公務員などもおり、それぞれの立場で学びが活かされているのではないかと思います。教育でも家庭科に限らず、例えば環境教育や人権教育など様々な分野に関わることですので、生活者としてすべての人が消費者教育の考え方を共有していることは重要だと考えています。
消費者教育で大事にしたいのは、消費者被害から学ぶことです。何か問題が表面化した時に、どの段階で動くかが大切だと思います。BSEのようにその問題が社会問題化することで法律やルールが変わることもありますし、初期の段階で手当てしておけば、重篤な被害も防げるかもしれません。最近のドラマに「パーソナル・イズ・ポリティカル(個人的なことは政治的なこと)」(※3)という言葉が出てきて、こういった考え方が日曜の学園ドラマの中で描き出されていることに感動しました。誰がどの時点で、その問題に真剣に向き合い、責任を持って動いていけるかで結果は変わってきます。
※3 「パーソナル・イズ・ポリティカル(個人的なことは政治的なこと)」
1960年代以降のアメリカにおける学生運動と第二波フェミニズム運動におけるスローガンで、私たちが日常で感じることや経験する問題は、社会全体の仕組みやルール、文化的な価値観と深く結びついているということ。
2022年からは資産形成も授業に加わりました。
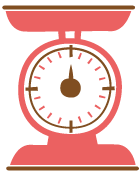 ルールがどんどん改正される年金や、NISAやiDeCoなどについて正確に伝えるのは教師だけでは難しいので、中立的な立場から金融経済に関するアドバイスを提供するJ-FLEC(金融経済教育推進機構)からアドバイザーを派遣してもらうことができます(HP上で教材も見れます)。私が取組んだ授業では金利や借金について学んだり、実際のキャッシュフロー表から資産形成のポートフォリオを考える必要性を学びました。生徒の感想には、もっといろんなバリエーションを知りたいという声もありました。自分がどんな生活をしていきたいかによって、どういったお金の稼ぎ方やふやし方をする必要があるかを知ることが大切です。
ルールがどんどん改正される年金や、NISAやiDeCoなどについて正確に伝えるのは教師だけでは難しいので、中立的な立場から金融経済に関するアドバイスを提供するJ-FLEC(金融経済教育推進機構)からアドバイザーを派遣してもらうことができます(HP上で教材も見れます)。私が取組んだ授業では金利や借金について学んだり、実際のキャッシュフロー表から資産形成のポートフォリオを考える必要性を学びました。生徒の感想には、もっといろんなバリエーションを知りたいという声もありました。自分がどんな生活をしていきたいかによって、どういったお金の稼ぎ方やふやし方をする必要があるかを知ることが大切です。
家庭科は社会や国の政策に連動する部分も多く、学ぶことは非常に広範囲ですが、生活の中でいかに自分のこととして考えるかが重要だと思います。金融商品だけが投資の対象ではなく、私たちの時間やお金を使って何を勉強するか、どんな企業や政治家を応援し、活動するのかという投資でも、社会や環境に対する私の発言力、私をコントロールする力は変わり得るということです。
ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。
 お子さんに習い事やどんな経験をさせてあげたいかも大事だとは思うのですが、私は毎日の暮らしの中で親子がお互いに、何を考え、感じているか分かり合いたいと思える関係性の中で、話し合えることこそが生涯の財産になると思っています。本音を言って共感し合える喜びや、相手の心の汲み方の良し悪しを知ることなど、生きていく上で重要なことは、信頼できる人間関係の中で育まれます。
お子さんに習い事やどんな経験をさせてあげたいかも大事だとは思うのですが、私は毎日の暮らしの中で親子がお互いに、何を考え、感じているか分かり合いたいと思える関係性の中で、話し合えることこそが生涯の財産になると思っています。本音を言って共感し合える喜びや、相手の心の汲み方の良し悪しを知ることなど、生きていく上で重要なことは、信頼できる人間関係の中で育まれます。
何気なく話した困りごとや怒りのエピソード、今日うれしかったことを回想する会話、そんな端々の情報を通じて感覚を分かち合う経験は、家族の関係性が変わってもなお、それぞれの人生を生き抜くための知恵袋として家族を支える力になるのかもしれません。